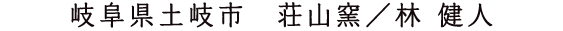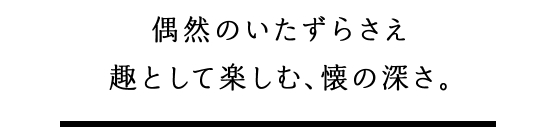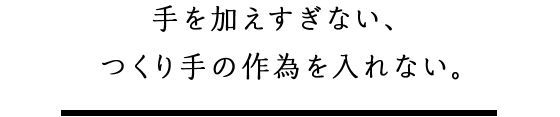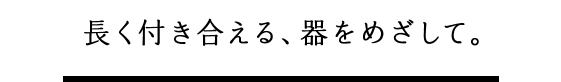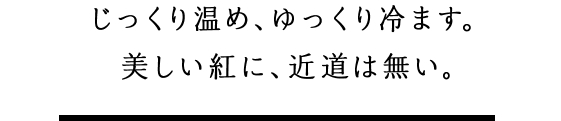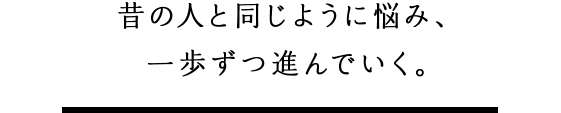日本でつくられる器の、およそ6割が「美濃焼」だと言われています。そんな美濃焼を代表する陶器のひとつ「志野(しの)」は、もともと偶然から生まれたものでした。
室町時代、ある窯元が茶の湯のために白い茶碗を焼き上げようとしたところ、思ってもみなかった色が出ました。その色を、失敗ではなく「趣がある」と捉えた陶工たちは、さまざまな工夫を重ね、鼠志野や絵志野、赤志野、紅志野といった、ゆたかな表現を生み出していきます。
このようなルーツを持つためでしょうか。志野には、土という素材の朴訥(ぼくとつ)さや、偶然のいたずらさえも趣として楽しみ、やんわりと包み込んでしまうような懐の深さがあります。

志野は一度、つくり手が途絶え、歴史の舞台からその姿を消します。しかし、昭和のはじめ、後に人間国宝となる荒川豊蔵が再現と復興を果たし、再びその魅力に光が当たるようになります。岐阜県土岐市にある荘山窯も、志野に魅せられた窯元のひとつ。親子二代にわたって「紅志野」を焼き続けてきました。
息子の林健人さんは、鮮やかな手つきでろくろを回し、器のかたちをつくり上げていきます。「ろくろは、できるだけ素早くを心がけています。つくり手の作為が入り込まない方が、飽きずに長く使ってもらえると思うのです」。人の手を加えすぎない、素朴な味わいをかもし出す器。それこそが志野の魅力だと言います。

「十草文様」と言われる文様をつけるときも、林さんはものさしやガイドを使わず、竹串だけでサッ、サッとまっすぐな線を引いてきます。「人の手でつくる以上、一見まっすぐに見える線にも細かな歪みが出てきます。しかし、その歪みもやがて味わいに変わり、見るたびに発見を与えてくれる。長く付き合える器とは、そういうものではないでしょうか」。
線状につけた溝に、今度は「いっちん」と呼ばれる技法で化粧土が流し込まれていきます。生地となる土に別の色の土を埋め込む「象嵌(ぞうがん)」という技法です。盛皿の表と裏、両方に象嵌を施すのは、修練を要する高度な技。職人として磨いた技と、作為の及ばない自然との調和。その絶妙なバランスが、紅志野の味わいを深めているのかもしれません。

紅志野のほのかな紅色は、鉄分が炭素に反応して起こる「還元」という作用から生まれるもの。一般的な陶器は、酸素との反応である「酸化」を利用して焼き上げますが、還元はそれよりも遥かに時間がかかります。一気に温度を上げすぎると、窯のなかに炭素が充満しきらず、還元作用が弱くなってしまうのです。
このため、一度にではなく徐々に火をつけ、窯の温度をじっくりと上げていきます。特に300℃までは、1日かけて様子を見ながら慎重に。そして、2日目から3日目にかけて、窯のなかは最高1100℃以上に達します。陶工たちは、窯に火を灯している間、ゆっくりと眠ることができません。外の風や湿気のわずかな違いによって火加減を微妙に変えながら、1時間に一度は窯の様子を見ます。窯の孔から溢れ出てくる炎の長さや色合いを見て、還元がどの程度の強さで進んでいるかを判断します。
「20年、陶工を続けてきたけれど、窯入れは毎回違う。ふたを開けてみるまでどう仕上がっているか分かりません。そこが、大変なところであり、楽しいところでもあります」。
火を消した後、さらに1日以上かけてゆっくりと窯の温度を冷まします。ここでも、焦ってはいけません。紅色の元である鉄分が、器の表面に出てくるには時間がかかるのです。

土と、釉薬(ゆうやく)に使われる長石という石だけ。紅志野の材料は、室町の時代と変わらず、至ってシンプルです。しかし、何十年と経験を積んでも、思った通りの仕上がりができるかは五分五分という世界。土と炎との、終わりの無い対話が続いていきます。
「昔の人も、同じ土を使い、同じやり方で、同じように悩みながら志野をつくっていたのでしょうね」。林さんは、志野のような純朴な笑顔とともに、楽しそうにつぶやきました。
単純だからこそ、奥が深まる。一見、華やかさはなくとも、「紅志野 盛鉢」は、静かに暮らしに寄り添い、付き合うほどに親しみを増す友となってくれるはずです。